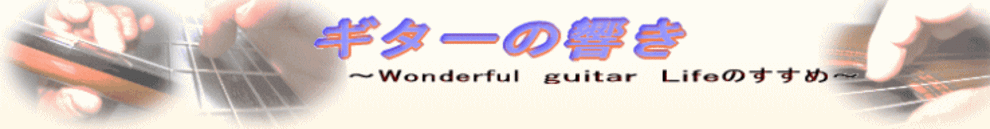今後のギターライフを発展させていくのに絶対に有効になります。
ひとつひとつの音階を覚えることは大変ですし
また覚えなくてもギターと言う楽器の特徴のひとつの「平行移動」と言うことをすれば
簡単に弾くことは出来ますので(これは更なるTrackでお話します。)
覚えるのではなく、どういうことかを理解しておいて下さればと想います。
ここで大分頭も混乱してきたと想いますので今までの所を
単純に機械的にまとめて見たいと想います。
コードの構成音のベース音になる部分はコードと同じ音です。
例 「C」と言うコードの場合のベース音は「C=ド」
「B」と言うコードの場合のベース音は「B=シ」
「F♯」と言うコードの場合のベース音は「F♯=ファ♯」
コードの後に余計なものがついていない場合は(mとか7とかdimなど)
構成音は「ベース音」「3度の音」「5度の音」の3つの音になります。
「3度の音」「5度の音」とは「ベース音」を含めて
「3番目と5番目の音」と言うことです。
何を基準に3番目の音、5番目の音を決めるかと言うと
そのコードに一番あった音階によって決めます。
音には
「ド・ド♯・レ・レ♯・ミ・ファ・ファ♯・ソ・ソ♯・ラ・ラ♯・シ」
と言う12種類しかありません。
そのコードに一番合った音階とは、その12種類の音の並びを見て
「ベース音」から間に何音入っているか、と言うルールによって決まります。
それはベース音からはじまって
「1音、1音、無し、1音、1音、1音、無し」
です。
そしてその音階を元にして「3度の音」と「5度の音」は決まります。
その音の重なりが
mとかmajとかが付いていない場合のコードの構成音になります。
お解かりでしょうか?
ちなみに、このような何も余計なものがついていない
「C」とか「G」と言う3つの音で構成されているコードを「トライアド」と言います。
これがコードの基本になります。
このような理論は別に知らなくてもギターは弾けます。
でもより極めていくと、必ずこのような話が出てきます。
知っているのと知らないのでは・・・知っているほうが絶対に役に立ちます。
例えばアドリブを奏でるとか、自分で好きな曲をアレンジするとか・・・。損はありませんよ。
実際にギターでどのように弾くのかは、章を追ってお話したいと想います。
とりあえず第1楽章はここまで。
お疲れ様でした。
| <【Track10】3度の音と5度の音 | ギターレクチャー理論編へ戻る |